レミエール症候群(以降LSと記載)とは、上気道感染に引き続く内頚静脈血栓および菌血症、さらには敗血症性肺塞栓までを一括りにした症候群であり、約80年前(1936年)にフランスの細菌学者レミエール博士が自験例20例をもとに報告したものです。内頚静脈の化膿性血栓は肺だけ でな く全身に遠隔転移し、転移性の膿瘍や塞栓を形成し、種々の症状を呈します。この先生、よく20例も集めたと思いますが、それもそのはず、当時はまだペニシリンなどの抗菌薬が登場する前の時代だったのです。
1960年代になり上気道感染にペニシリンなどの抗菌薬が使用されるようになるとLSの罹患率は急激に減少し、“忘れ去られた病気(forgotten disease)”と呼ばれるようになりました。しかし1990年代から再び罹患率が増加したのは、上気道炎に対する抗菌薬の使用が制限されるようになったことが原因ではないかと推測されています。起炎菌は口腔内の常在菌であるFusobacterium属(F. necrophorumが主)が圧倒的に多く(90%)、一般に、血液培養でこの菌が検出されることが、本症の診断根拠となります。
初期症状は咽頭痛、頸部痛、発熱などの上気道炎症状ですが、この段階でLSが疑われることはなく、その後の内頚静脈の血栓性静脈炎の症状(頸部痛、頸部腫脹)や、それが遠隔転移した諸症状をもってLSが疑われます。諸症状とは、血栓性肺塞栓症による呼吸困難が重要ですが、その他にも、肝膿瘍の存在、化膿性脊椎炎による腰痛、脳膿瘍による症候性てんかん、などなど多彩な症状・所見を呈します。加えて血液培養からFusobacterium属が検出されることで本症の診断に至る、という診療のストーリーになります。
本症は小児や易感染性宿主(高齢者や基 礎疾患保有者)にも発症しますが、好発するのは30代前後の健康成人とされています。健康な成人が咽頭炎をこじらせて、非常に重篤な症状やバイタルサイン(ショックやSpO2低下など)を呈して来院するケースでは、本症を鑑別に挙げる必要があります。治療は、βラクタマーゼ耐性、および複数菌感染を考慮して、初期はABPC-SBTなどの広域βラクタマーゼ阻害剤が選ばれますが、Fusobacterium属と確定された後はメトロニダゾールの有用性も多く報告されています。(文責:佐野/新井)
参考リンク:http://appliedradiology.com/articles/lemierres-syndrome
(内頚静脈血栓と敗血症性肺塞栓のCT写真はこちら)
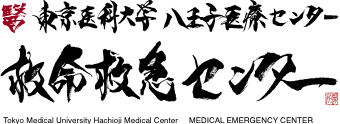
 救急科専門研修
救急科専門研修 見学・お問い合わせ
見学・お問い合わせ
